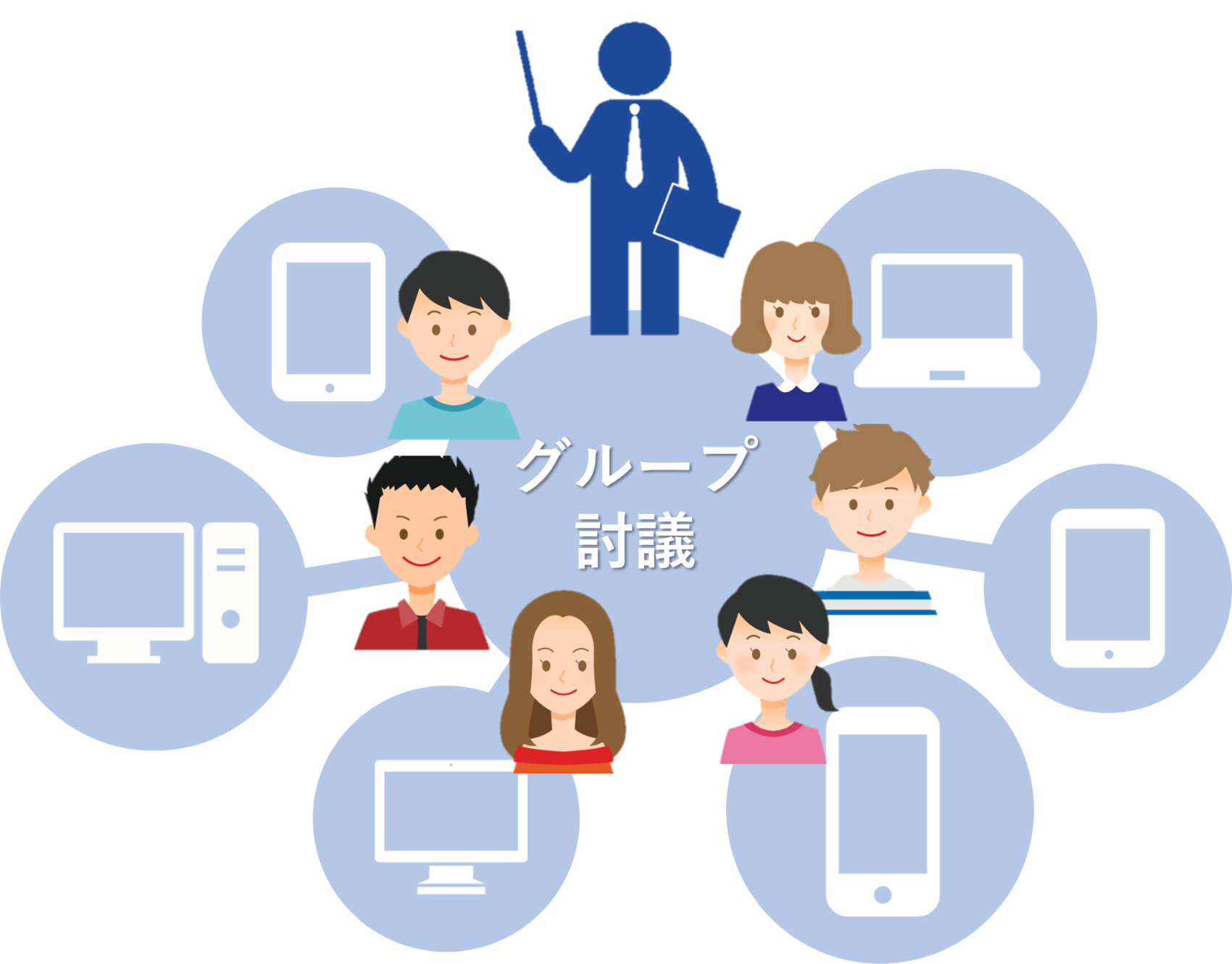職長を務めるにあたっては、職長教育の受講が必要ですが、職長教育のカリキュラムでは、「職長教育グループ討議」という活動を行います。
職長教育グループ討議はどのような目的があり、具体的に何をするのか、職長を志す方は気になるところでしょう。
そこで今回は、職長教育グループ討議の内容のほか、職長教育のWebでの受講方法などについて解説します。
目次
職長教育グループ討議の内容

職長は、作業現場において作業員を指導監督する重要な役割を担います。まずは、そんな職長になるための職長教育のグループ討議の目的、討議で実践する課題の内容を解説します。
職長教育グループ討議とは?
職長教育グループ討議とは、職長教育で行うグループワーク、グループディスカッションのことです。講習機関によっては「グループ演習」などと少し違う名称で呼んでいる場合もありますが、やることは基本的に同じです。
職長教育の参加者で4人~7人のグループを作り、議長・書記・発表・コメント役など、メンバーごとの役割分担を決めます。それぞれの役割が決まったら、与えられた課題に対し、グループ内で考え、結論を出すという流れです。

職長として的確な指示が出せるよう、行動の目的や意味を理解することが職長教育グループ討議の目的です。コメントにおいても、良い部分、悪い部分、改善点などの具体的な意見を出すことが要求されます。
このようなグループワークを通して、部下を指導する職長に必要な、良い部分を褒める、細かい部分に気付く、的確に助言するといった指導方法を体で覚えていきます。

なお、職長教育グループ討議中は、声の大きさ、話し方のリズム、姿勢、立ち振る舞いなどもチェックされます。
職長は作業現場の安全を担うため、厳しい要求が与えられるケースもあるようです。
次に、職長教育グループ討議の3つの課題について詳しく見ていきましょう。
課題(1)健康KY演技
健康KYとは、職長が作業員に睡眠・食欲・体調に関する3つの声かけを行い、日々の体調変化を把握する活動のことです。ストレスは労働災害を招く大きな要因であるため、ストレスの有無をチェックするメンタルヘルス対策として、健康KYは有効な手段となります。

職長教育グループ討議では、健康KYの実践に必要なコミュニケーションの取り方、健康確認の方法を学んだうえで適正な配置を理解します。
課題(2)危険予知訓練
危険予知訓練とは、職場や作業に潜む危険要因を話し合い、危険に対する感受性や問題解決能力を高める訓練のことです。危険要因を潜在意識に落とし込み、危険箇所と行動目標を指差し呼称で習慣化することで、ヒューマンエラーによる事故防止につなげます。
グループ討議では危険回避だけでなく、正しい作業手順をもとに、行動目標を立てる重要性を理解します。

危険予知訓練は、労働災害のプロセスを倫理的に考え、指差し呼称の意味と効果を把握できるトレーニングです。
課題(3)リスクアセスメント
リスクアセスメントとは、現場に潜む危険性、有害性のあるものを除去、低減する手法のことです。自主的に危険箇所や有害な要因を見つけ出すことで、事前に的確な対策を講じることが可能になります。
職長教育グループ討議では、人の行動による労働災害防止活動の限界を機械設備で解決する、という考え方を理解します。
「安全=経営の安定」につながることを、職長の立場で理解するのがリスクアセスメントを学ぶ目的です。
職長教育の受講方法とは?
職長教育は、労基連や各協会が指定した会場、またはWebで受講することができます。
労基連や各協会の講習会では、2日間拘束されるうえに、平日のみの開催である場合もあります。

したがって、仕事が休めない、時間が取れないという方には、Web講座がおすすめです。
講習会の職長教育グループ討議は対面で行いますが、Web講座ではビデオ通話を使って実施します。
ビデオ通話でも対面と同様に、講師が討議の内容に対して随時コメントや指導を行います。

ビデオ通話はスマートフォンからでも利用できるため、オンライン環境があればどこからでも職長教育グループ討議に参加が可能です。
また、職長教育グループ討議を除き、職長教育の講義は動画やテキストで勉強できます。
職長として実務に役立つ知識をいつでも復習できるのは、Web講座の強みといえるでしょう。
職長教育グループ討議は、職長としての職務に役立つ
職長は作業員に対する指導監督者で、作業員の安全を守り、労働災害を防止する職務を担います。職長になるために受講する職長教育では、職長に必要な指導力や対応力を身につける職長教育グループ討議を行います。
職長教育グループ討議の課題としては、健康KY演技、危険予知訓練、リスクアセスメントが代表的です。いずれも作業員の安全を守る重要な課題であるため、目的や効果をしっかりと把握しておきましょう。
先ほども紹介しましたが、職長教育の講習会は2日間を要するため、仕事が忙しく時間が取れない方はWeb講座の受講がおすすめです。

Web講座では、スマートフォンから参加できるうえに、職長教育の内容は動画やテキストでいつでも勉強できます。忙しい方はもちろん、職長教育の理解を深めたい方はWeb講座を活用しましょう。