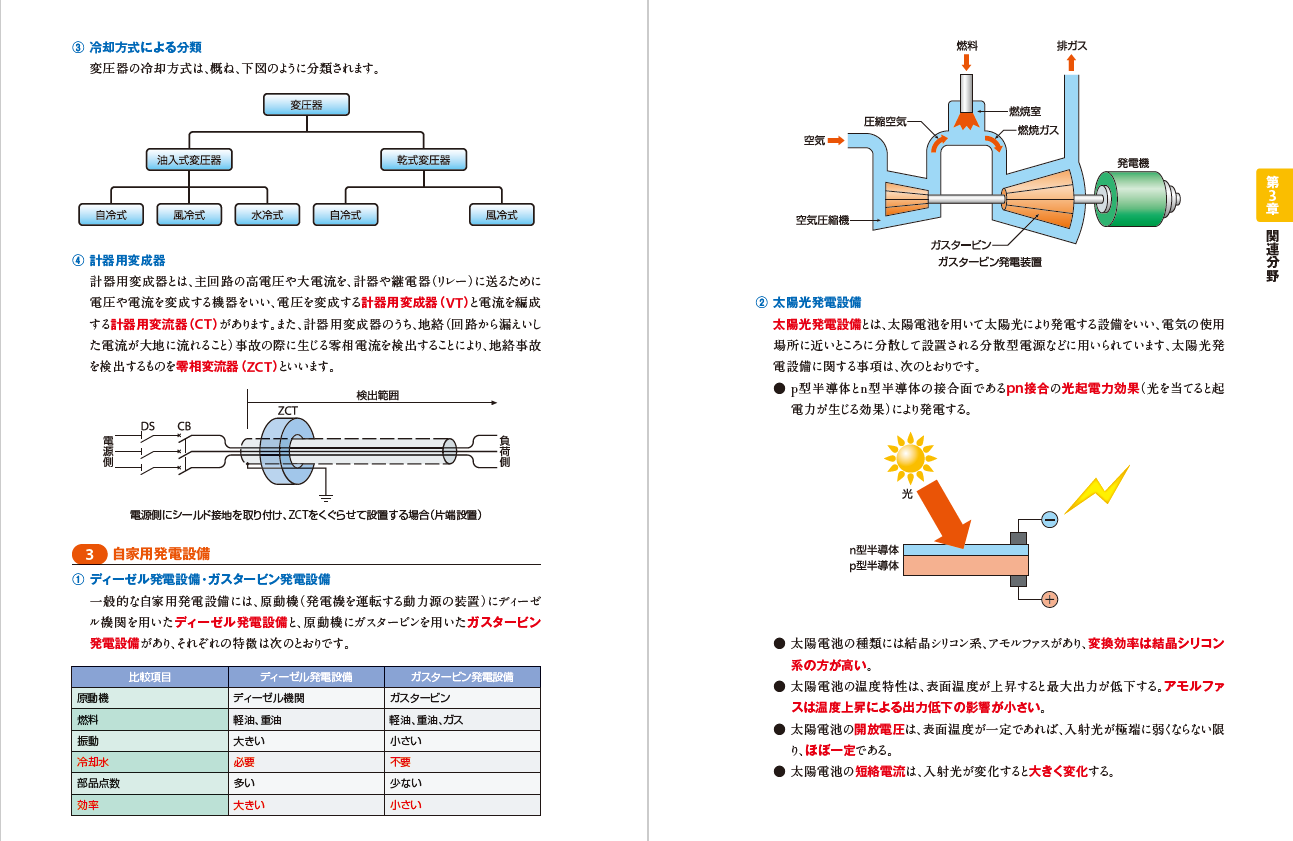電気通信工事施工管理技士は、携帯電話やインターネットなどの通信設備工事に携わるために必要な資格です。近年、「5G」や次世代規格の「6G」「7G」などの基地局の建設需要なども高まっており、電気通信工事施工管理技士の取得を目指す方も多いでしょう。
電気通信工事施工管理技士の受験資格は学歴のほかに、指定学科卒業の有無で実務経験年数が変わります。
今回は、電気通信工事施工管理技士の指定学科の概要を踏まえ、指定学科以外を卒業したケースの相違点について解説します。
目次
電気通信工事施工管理技士の指定学科とは?
冒頭でも述べた通り、電気通信工事施工管理技士の受験資格には実務経験がありますが、指定学科を卒業している場合と卒業していない場合、実務経験の必要年数が大きく違います。
電気通信工事施工管理技士の受験資格にある、指定学科を全て紹介します。また、指定学科以外でも、指定学科に準ずると認められるケースもあわせて確認しましょう。
電気通信工事施工管理技士の指定学科一覧
電気通信工事施工管理技士の指定学科は、「電気通信学、電気、土木・農業、都市工学、機械、建築」という、6つの学科コードで以下のように分類されます。
| 学科 コード |
指定学科 |
|---|---|
| 01 | 電気通信(工)学科 |
| 02 | 電気(工学)科 / 応用電子工学科 / システム工学科/ 情報工学科 情報電子(工学)科 / 制御工学科 / 通信工学科 / 電気技術科 電気工学第二科 / 電気情報(工学)科 / 電気設備(工学)科 / 電気・電子(工学)科 電気電子システム工学科 / 電気電子情報(工学)科/ 電子(工学)科/ 電子応用工学科 電子技術科/ 電子工業科/ 電子システム工学科/ 電子情報(工学)科 電子情報システム(工学)科/ 電子通信(工)学科 / 電子電気工学科 / 電波通信学科 / 電力科 |
| 03 | 土木(工学)科 / 開発工学科 / 海洋開発(工学)科 / 海洋工学科 / 海洋土木工学科 / 環境開発科 / 環境建設科 / 環境整備工学科 / 環境設計工学科環境土木科 / 建設(工学)科 / 建設環境工学科 / 建設技術科 / 建設基礎工学科 / 建設工業科 / 建設システム(工学)科 / 建築土木科 / 構造工学科 / 資源開発工学科 / 社会開発工学科 / 社会建設工学科 / 水工土木(工)学科 / 地質工学科 / 土木海洋工学科 / 土木環境工学科 / 土木建設工学科 / 土木建築(工学)科 / 土木地質科 / 学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻 |
| 農業土木(学)科 / 生活環境科学科 / 生産環境工学科 / 地域開発科学科 農業開発科 / 農業技術学科 / 農林工学科 / 農林土木科 / 農業工学科 農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学及び宮崎大学以外については、農業機械学専攻、専修又はコースを除く) 学科名に関係なく農業土木学コース・講座・専修・専攻 学科名に関係なく農業工学コース・講座・専修・専攻 |
|
| 森林土木(学)科 / 森林工学科 / 林業工学科 / 林業土木科 / 緑地(学)科 環境(工学)科 / 環境緑化科 / 環境緑地科 / 緑地園芸科 / 緑地工学科 緑地土木科 / 林業緑地科 / 造園(学)科 / 環境造園科 / 造園工学科 造園土木科 / 造園緑地科 / 造園林学科 / 造園デザイン(工学)科 鉱山土木学科 / 砂防学科 / 治山学科 |
|
| 04 | 都市工学科 / 環境都市工学科 / 都市システム(工学)科 |
| 05 | 機械(工学)科 / エネルギー機械工学科 / 応用機械工学科 / 機械技術科 機械工学第二科 / 機械工作科 / 機械航空工学科 / 機械システム(工学)科 機械情報(システム)工学科 / 機械精密システム工学科 / 機械設計科 機械電気(工学)科 / 建設機械科 / 航空宇宙システム工学科 / 航空(工学)科 航空宇宙(工)学科 / 交通機械(工)学科 / 産業機械(工学)科 自動車(工業)科 / 自動車工学科 / 精密工学科 / 精密機械(工学)科 生産機械(工学)科 / 船舶工学科 / 船舶海洋(システム)工学科 / 造船科 電子機械(工学)科 / 電子制御機械工学科 / 動力機械工学科 / 農業機械(学)科 学科名に関係なく 機械(工学)コース |
| 06 | 建築(学)科 / 環境計画学科 / 建築システム科 / 建築設備工学科 建築工学科 / 建築第二学科 / 住居科 / 住居デザイン科 / 造形工学科 環境計画学科 / 建築システム科 / 建築設備工学科 建築工学科 / 建築第二学科 / 住居科 / 住居デザイン科 / 造形工学科 |
上記のとおり、指定学科と認められる学科は多岐に渡ります。
指定学科の学歴は、「大学・短大・高等専門学校(5年制以上)・専門学校(高度専門士または専門士)・高校・中学」と、全ての学歴で指定学科は共通です。
また、学校によっては入学時期を指定するケースもあるため、受験前に確認しておきましょう。
指定学科に準ずると認められる学校・学科もある
先に紹介した指定学科に該当しない場合でも、「指定学科に準ずると認められる学校・学科」に該当すれば指定学科卒と同じ扱いになります。
そこで、大学・高等専門学校・高校に多く該当する学科を、一部抜粋して紹介します。
| 学歴 | 学部・学科 |
|---|---|
| 大学 | 電気システム工学科 / 電子光システム学科 / 電気情報物理工学科 都市開発学科 / 都市環境工学科 / 社会環境工学科 / 環境建設工学科 環境システム学科 / 建築環境学科 / 環境デザイン学科 / 建設工学科 情報システム工学科 / 情報通信工学科 / 情報・通信工学科 農業環境工学科 / 緑地環境学科 / 海洋建築工学科 / 機械工学科 機械知能工学科 / 機械制御工学科 / 機械物理工学科 / 機械電子工学科 まちづくり学科 / 建築デザイン学科 / 建築創造学科 / 建築都市学科 |
| 高等専門学校 | 制御情報工学科 / 電子制御工学科 / 建築環境工学科 / 環境都市工学科 |
| 高校 | 情報通信工学科 / 電気システム科 / 電気・情報システム科 / 電気技術科 土木システム科 / 農業土木科 / 緑地土木科 / 緑地環境科 都市環境科 / 都市工学科 / 都市デザイン科 /環境都市工学科 電子電気科 / 電子機械科 / 機械システム科 / 機械工学科 建築科 / 建築システム科 / 建築デザイン科 / 建築インテリア科 |
出典:一般財団法人 全国建設研修センター ※一部の学科を抜粋

指定学科に準ずると認められるのは学科だけでなく、学科内の専攻やコース、講座も含まれます。
電気通信工事施工管理技士と指定学科の関係性

電気通信工事施工管理技士で指定学科を設けている理由と、指定学科以外を卒業した場合の違いを見ていきましょう。
電気通信工事施工管理技士の受験資格に指定学科がある意義
電気通信工事施工管理技士に指定学科、および指定学科に準ずる学校・学科を定めているのは、国土交通省令です。

指定学科を卒業すると、受験資格の実務経験が指定学科以外よりも1年半~2年半ほど短縮されます。
また、2級電気通信工事施工管理技士の合格者が1級を受験する場合や、専任の主任技術者の経験が1年以上ある場合でも、指定学科卒は実務経験が短くなります。
指定学科以外を卒業した場合よりも、いち早く試験を受験できるのが指定学科の存在意義といえるでしょう。
ただし、指定学科が関係するのは、第一次・第二次検定を両方受験するときに限ります。
第二次検定のみを受験する際は、第一次検定に合格、または技術士の取得などで受験が可能です。
指定学科以外で卒業した場合はどうなる?
指定学科に該当しない学部や学科を卒業した場合、受験資格の実務経験が指定学科卒より長くなります。
例えば、学歴要件で第一次・第二次検定を受験する場合、「大学・専門学校(高度専門士)・高校・中学は1年半」、「短大・専門学校(専門士)・高等専門学校は2年半」となります。
ただし、実務経験年数が15年以上ある場合、指定学科、指定学科以外の学歴要件なしで受験が可能です。
2021年度の4月より施工管理技士の受験資格が緩和された
2021年度の4月より電気通信工事施工管理技士を含む施工管理技士全般の受験資格が緩和されました。これにより、2級の第二次検定合格者が1級の第一次検定を受験する場合に限って受験資格が不要です。
第二次検定を受験する際には合格後5年以上の実務経験が必要ですが、2級の第二次検定合格の翌年から、1級の第一次検定は受験できます。
また、第一次検定の合格者には新規資格である「技士補」が付与されます。技士補が付与されると第一次検定が免除されて第二次検定を何度でも受験できるようになりました。
技士補になると監理技術者の配置義務が緩和されるといったメリットもあるため、電気通信工事施工管理技士を目指す方にとっては、大きなチャンスといえるでしょう。実務経験を積みながら、受験できる資格区分から積極的に臨んでください。
電気通信工事施工管理技士の指定学科は幅広い
電気通信工事施工管理技士の受験資格にある指定学科は、電気通信系や情報系、建築系といった業務に関連する学科が該当します。また、指定学科に準ずる学校や学部を卒業すると、指定学科と同じ条件で受験が可能です。
指定学科を卒業すると実務経験年数が優遇され、指定学科以外を卒業した人よりも早く受験資格が得られます。指定学科以外を卒業した場合、1年半~2年半ほど実務経験年数が長くなることを心得ておきましょう。
電気通信工事施工管理技士は、インターネットや電話など、生活に欠かせないインフラを支える重要な役割を果たします。
電気通信工事施工管理技士の勉強は通信講座でもできる
指定学科を卒業している場合でも、電気通信工事施工管理技士の資格を得るためには試験を受験する必要があります。
電気通信工事施工管理技士の一次はマークシート式、二次は記述式での解答が求められるので、それぞれ別の対策が必要です。
資格学校へ通学して勉強することも可能ですが、実務経験が必要な電気通信施工管理技士の勉強は好きな時間に勉強ができる通信講座がおすすめです。
例えば、SATの通信講座は講義動画とテキストの2つを使って学習を進めます。講義動画は1講座10~20分前後なので、忙しい人でもちょっとスキマ時間で学習を進めることができます。
またテキストもフルカラーでイラストや図が豊富で、視覚的にも学習できるので記憶に残りやすい工夫がされています。

通信事業に携わる方は、受験前に自身の学歴が指定学科に該当するかしっかり確認し、資格取得に向けての一歩を踏み出しましょう。