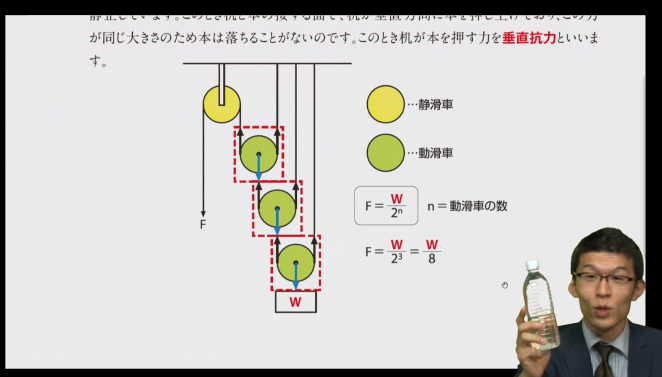消防設備のメンテナンスや工事ができるスペシャリストである消防設備士。
甲種第1類資格を取得することで、より専門性が高い消防設備に携わることができます。国家資格としても注目されている消防設備士甲1資格はどのような資格なのでしょうか、資格の概要から取得方法まで詳しく解説していきます。
目次
そもそも消防設備士はどんな資格?

公衆が出入りする建物には、用途や規模や収容人員に応じて屋内消火栓というような消防用設備などの設置が法律で義務付けられています。
消防設備士は、この消防用設備の工事や整備・点検を行うことができる資格です。
消防設備士はどんな仕事をするの?
消防設備士の資格を保有することで、消防用設備の工事や整備、点検の仕事に就くことができます。
法令に基づいた知識や技能なども兼ね備えており、防火面でのスペシャリストとして認められる資格です。
消防設備を販売・メンテナンスする会社やビルメンテナンス会社などで働くことができます。また消防設備工事の施工管理の仕事なども引き受けることが可能となります。
ただし、資格取得後は研鑽努力が求められます。消防設備士として従事している人は、日々変わる法令のほか、最新の知識や技能を習得するために数年に一度都道府県が設定する講習を受講する義務が課せられます。
消防設備士甲1資格では何ができる?
消防設備士は、免許種別があります。甲種と乙種、2種類があり、甲種では整備や点検、工事施工が可能になります。乙種の場合は整備や点検のみの資格となります。
また消防設備士は工事整備対象設備ごとにカテゴリ分けがなされており、特類と1類~7類(6類・7類は乙種のみ)の8つのカテゴリに分けられています。
この中で、甲種第一類の場合は、以下の通りの設備が対象です。
| 1 | 屋内消火栓設備 |
|---|---|
| 2 | スプリンクラー設備 |
| 3 | 水噴霧消火設備 |
| 4 | 屋外消火栓設備 |
| 5 | パッケージ型消火設備 |
| 6 | パッケージ型自動消火設備 |
| 7 | 共同住宅用スプリンクラー設備 |
主にスプリンクラーや消火栓といった、学校や商業施設、ビル・マンションなどに導入されている消防設備に関する資格となります。

これらの設備は実際に稼働させたうえで点検することが難しいため、日々の点検整備が重要な役割を占めているということは言うまでもないでしょう。
甲1・消防設備士の資格を取得する方法

先ほど紹介した通り、消防設備士甲種1類はスプリンクラーなどの多くの施設で導入されている設備を扱うことができますので、資格取得は必ず仕事に直結します。ここからは、甲1の資格取得方法をお伝えします。
厳しい甲種の受験資格
甲種の消防設備士には受験資格が存在します。
- 指定された国家資格を保有していること
- 実務経験を有すること
- 指定学科がある大学や高校(中等教育学校等)を卒業していること
以上のものなどが含まれます。
条件の中でいずれか一つを満たせば受験資格が得られますが、「乙種第1類を取得後2年以上の実務経験を有するもの」というように取得後の実務経験を求められるものもあります。
試験は全国で受験可能
消防設備士の試験は、全国主要都市で行われ、一つの地区で年に3~4回開催されています。甲種1類試験の場合、2~3ヶ月に1度のペースで行っている地域も存在しているので、受験地を変えて受験のチャンスを広げることも可能です。
特に東京エリアでは、2ヶ月に1度の受験チャンスがありますので、自分が住む都道府県での受験で不合格だった場合でも東京で受験するという考え方もできます。
合格基準は、科目ごとの正答率が40%以上、かつ試験科目全体の正答率が60%とされています。トータルで60%の正答があっても、科目免除を受けている場合などに不合格となる場合があるので注意が必要です。
気になる消防設備士甲1の合格率は?
甲種の中で一番受験者数が多い消防設備士甲1資格。その合格率が気になります。試験を管轄している消防試験研究センターの発表では、令和6年度が24.1%、令和5年度が22.3%、令和4年度が23.7%と例年30%に満たない合格率で推移しています。狭き門ですが、合格後はスペシャリストとして優遇してもらえます。
試験は四者択一方式のマークシートによる筆記試験と実技試験があります。実技といっても机上での記述式ペーパテストです。名称の問いや製図、計算式などの記述が求められます。

法令を正しく覚えるほか、語句や計算式を正しく記入できるかが、合格の可能性を高めるカギとなるでしょう。
消防設備士甲1に合格する勉強法とは
消防設備士の筆記試験の難易度は、計算問題ですと中学~高校1年レベルに相当するので、参考書を理解するまで読み込み、問題集を3回以上繰り返せば、合格に近づきます。
また、すでに関連資格を取得している方は、分野によって十分な知識があるため、不足している部分を見定めて勉強時間を調整しましょう。
職場や身近な素材で勉強すると記憶に残りやすいので、おすすめです。例えば、消火栓や自動火災報知、スプリンクラー設備など現場の上司や知り合いに見学をお願いするなど、実際に見ることができる環境はどんどん利用しましょう。
そして、法令や規格、設置基準などの勉強はとにかく覚えることが重要になるので、通勤時間や仕事の休憩中も勉強ができる暗記カードもおすすめです。
まずは乙種から受験することもおすすめ
もし消防設備士の勉強に対して自信がない人や、受験資格を満たさない方は、甲種からではなく乙種から受験をしてみることもおすすめです。甲種では整備と点検だけでなく工事に関する知識も問われます。
一方で、乙種は工事に関する問題は出題されません。つまり勉強する範囲が乙種の方が狭いということになります。
例えば、乙種の中でも消防設備士乙種6類は消化器に関する資格です。一般住宅はもちろん大型の施設やビルにも必ず置いてある消防設備ですので、資格の需要もとても大きいです。例年、甲種乙種の全ての類を比較しても、乙種6類の受験者数が一番多いです。
最近では消防設備士をオンラインでも勉強ができる通信講座もあります。オンラインの通信講座は動画とテキストで勉強するという方法を採用しており、2つを効果的に使うことで勉強の理解度が深まるといった特徴があります。

消防設備士はビルメンテナンス業を中心にあらゆる業界で需要のある資格です。ぜひ取得を目指してみてください。